一学期終業式後に、福島県手話通訳問題研究会のボランティアの皆様による読み聞かせ
会が行われました。幼児児童の興味関心のある絵本やジャンルを事前にお伝えし、当日は、
幼稚部、小学部それぞれに合わせた読み聞かせを行ってくださいました。
読み聞かせの他にも、ペープサートによる劇や手遊び歌などもあり、みんなで楽しむこ
とができました。また、『したきりすずめ』では、表情や手話表現での語りに子どもたち
がぐっと惹き込まれていました。
手話通訳問題研究会の皆様、お忙しい中、素敵な読み聞かせを行っていただきありがと
うございました。




7月20日(木)に第1学期の終業式を実施しました。分校長先生のお話では、写真を見
ながら1学期の学習活動を振り返りました。子どもたちは、思い出を生き生きと表現する姿
が見られ、充実した1学期であったことがよく伝わってきました。
その後、各学級で担任から1人1人通知表が手渡されました。1学期がんばったことをそれ
ぞれ振りかえると共に、明日から始まる夏休みへの期待に胸をふくらませている様子でした。
また、保護者の皆様には、奉仕活動として校内の清掃活動をしていただき校舎がピカピカに
なりました。また、日頃から教育活動に対するご理解やご協力をいただき、無事に1学期を
終えることができましたことに感謝申し上げます。
また2学期の始業式に元気に会えることを楽しみにしています。




7月7日(金)に、県内の聴覚支援学校に通う幼児が聴覚支援学校本校に集い、交流会を
行いました。この日は七夕ということもあり、各幼児が考えた願い事を発表したり、みんな
で一緒に短冊を飾ったりしました。
自己紹介や願い事発表が終わった後はプールでの活動を行いました。大きなプールに子ども
達は大興奮!友達が泳いでいる様子を見て真似てプカプカ泳いだり、他校の友達との水中カ
ルタが白熱したやりとりになったりと、集団での水遊びを楽しむことができました。
また、今回は昼食も共にし、他校の友達と一緒にお弁当を食べました。「あ、ブロッコリー
が同じだ。」「わかめおにぎり、私もあるよ。」と伝えながら食べる様子が見られ、楽しい
コミュニケーションの時間となりました。
次に本分校交流会が行われるのは11月です。また、一緒に遊んだりやりとりしたりする
日を楽しみに過ごしていきたいと思います。




福島市立信夫中学校からの依頼を受け、『聞こえにくさ(聴覚障がい)について学ぼう』の
講義を行いました。福祉体験活動の学習の一環で、実技も取り入れた講義を行いました。
聞こえにくさの疑似体験、補聴器試聴体験、指文字・手話の体験を通して、きこえにくさ
があることの困難さ、補聴器、指文字、手話の有用性などについて実感していただきなが
ら、講義を進めることができました。
講義後の生徒代表の挨拶の中で、「みんなが住みやすい社会にするために、これからの
自分にできることを考えて実践していきたい。」という言葉を聞き、大変うれしく思いま
した。今回の講義と体験が、生徒さんたちの今後の生活につながっていくことを願ってい
ます。






6月の聴器点検は、ミミプラザさんにお越しいただき、小学部低学年の児童を対象に実施し
ました。前日の全体自立活動でイヤモールドの掃除をがんばったAさんは、「とてもきれいで
す。」とお褒めの言葉をいただき、嬉しそうにしていました。フックがゆるんでいた補聴器に
は、小さなゴムを入れていただき、ゆるみも解消。その細やかな作業を食い入るように見つめ
るBさんでした。子どもたちのよりよいきこえのためにいつもありがとうございます!


7月4日(火)に、福島大学からの依頼を受け『聴覚支援学校で学ぶ子ども
たち』の講義を行いました。この講義は特別支援教育に関する講座の1つで、1
年生の約90名の学生が参加しました。
講義では、耳のしくみや補聴器、人口内耳について、聞こえない人たちの生活
を知り、考える内容、また、実際に補聴器や補聴援助システムの試聴体験等を行
いました。また、聴覚支援学校福島校の学校紹介をはじめ、学校の特色や聴覚障
がい教育についての内容を取り上げました。
メモを取りながら最後まで熱心に講義に御参加くださった学生の皆さん、ありが
とうございました。
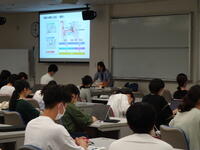



6月27日に「みみちゃん教室(乳幼児を対象とした集団での教育相談)」を開催しまし
た。今回は、4組の親子が遊びに来ました。初めて会うお友達同士もボールプールの中で
すぐに仲良しになっていました。また、新聞紙を破いた間からボールを投げたり、顔を出
して覗いたり、くしゃくしゃにして新聞紙の感触を味わったりと、それぞれの遊びを展開
していました。 7月は、水遊びを予定しています。次回も、一緒に楽しい時間を過ごし
ましょう!





小学部では、年2回補聴器や人工内耳について学ぶ自立活動の時間を設けています。
普段は、個別学習や小集団での自立活動を行っていますが、この2回は、小学部全員
で学習に取り組みます。
今回は、第1回目の学習で、「いつ補聴器を外すか。」「外した補聴器はどこに置か。」「だれが管理しているか。」等の普段の様子を振り返るところから学習しました。
その後、電池残量やイヤモールドのお手入れの仕方を確認し、実際に自分で実践しました。
学んだことを必要な場面でできるよう、ご家庭と協力しながら今後も支援していきたいと
思います。







6月22日(木)、アクアマリンふくしまから移動水族館がやってきました。子ども達は
前日から「どんなお魚が来るかな?」「どうやって来るの?」とワクワクし、当日は間近で
見る大きなトラックを見て大興奮な様子でした。
初めにハンズオンという水生生物のはく製や標本に触り、実物大のマンボウの大きさを体
験してみたり、サメの歯のギザギザ感やゴマフアザラシの皮膚の柔らかさに触れたりしまし
た。次にタッチプールという、ヒトデやウニ、トラザメやナマコ等と実際にふれあえる体験
を行いました。どの展示も子ども達の興味を引く物ばかりで、「これなぁに?」と興味津々
に触ったり水族館の職員の方からお話を聞いたりし、大盛り上がりでした。
今回の体験を通して、海の生き物の不思議さや新しい発見をたくさんでき、子ども達にと
って貴重な思い出になりました。
アクアマリンふくしまの皆様、貴重な体験をさせていただきありがとうございました。





5年生の家庭科で「ゆでて食べよう!」の授業を行いました。
コンロの安全な使い方、お湯の沸かし方、沸騰の様子等の既習の復習をし、「ゆでいも」を
作りました。洗う、切る、ゆでるの流れに沿って、一つ一つ丁寧に行っていました。
じゃがいもの過熱の過程で、いもの様子を観察したり、試食したりしました。いもの中が生
だったり、食べても硬かったりと、加熱時間による変化に気付くことができました。
今後の調理活動に意欲がわいた時間になりました。



